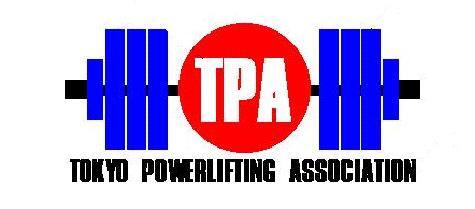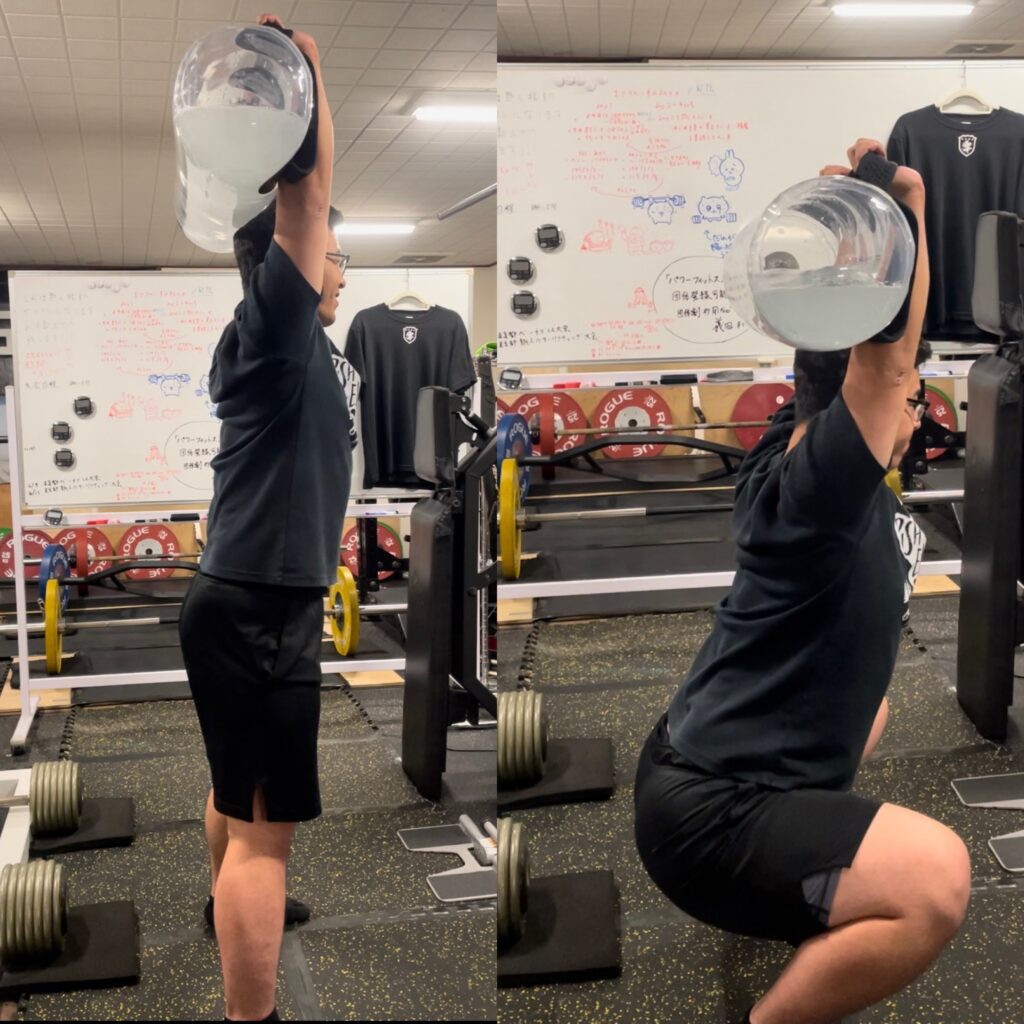京王井の頭線浜田山駅近くにある本格的なフリーウェイト特化型ジム、パワーフィットスタジオZEROの義田です。
東京都内でパワーリフティング練習もできるコスパの良いフィットネスジムにもなります。
「サイクルトレーニングは管理しやすくて便利なプログラム!」
「サイクル序盤は軽いのでフォーム練習、後半は重量挑戦とバランスが良い」
しかし、
「必ずしもサイクル後半で調子を合わせることが出来ない」
「最近停滞してきたし怪我も増えてきた・・・」
など、サイクルトレーニングは取り入れやすい反面、一長一短あります。
今回はそんなトレーニングプログラムのサイクルトレーニングのデメリットの説明と、そのデメリットを解消するRPEベースのサイクルトレーニングを提案致します。
サイクルトレーニングを取り入れたい方、サイクルトレーニングで停滞している方は是非この記事を参考にしてみてください。
過去にサイクルトレーニングを説明していますので、サイクルトレーニングの詳細はこちらを参考にしてみてください。
・追い込むだけでは成長しない!?中級者以上のトレーニングプログラムについて
https://power-fit-studio-zero.com/chx55119/intermediate-training-program/
目次
まずサイクルトレーニングとは何か?
サイクルトレーニングは過去記事にて具体的に説明していますので、今回は簡潔に説明します。
イメージとしては4~6週間1サイクルでピークを作って自己ベストを達成し、そこから+2.5㎏増やして次のサイクルを実施します。
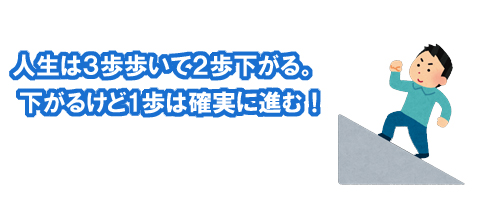
例えば、今までのスクワットの自己ベストレップが130㎏8回だとします。
4週間後に132.5㎏8回挙上を目標に、毎週+7.5kg刻みでサイクルトレーニングを組みます。
4週目:132.5㎏8回2セット(1セットでも達成出来ればOK)
3週目:125㎏8回2セット、メモリーセット132.5㎏4回
2週目:117.5㎏8回2セット、メモリーセット125㎏4回
1週目:110㎏8回2セット、メモリーセット117.5㎏4回
となります。
4週目で132.5㎏8回を1セットでも達成したら、次のサイクルでは4週目で+2.5㎏増やした135㎏8回になるようにプログラムを組み直します。
サイクルトレーニング序盤、1週目2週目はかなり軽くて余裕がありますので、フォームを丁寧に挙上スピードを意識していきましょう。
また、スクワットの補強種目(ブルガリアンスクワット、フロントスクワット、その他マシントレーニング)はサイクルトレーニング序盤1~2週目は多く実施、終盤の3~4週目は補強種目を少なくするか実施しないのがおススメです。
私はサイクルトレーニング序盤の補強種目はそれぞれしっかり3セット実施し、サイクルトレーニング終盤は軽い負荷で2セットだけ実施するようにしています。
サイクルトレーニング成功の秘訣は、軽い負荷の時期であるサイクルトレーニング序盤を我慢できるかです笑
私も導入初期は「こんな軽くて筋肉衰えないのか?」と心配でしたが、きちんとサイクルトレーニング通りに実施したら1ヶ月ごとに+2.5kgづつ、計+15㎏くらい自己ベストを更新できました!
トレーニング初心者~中級者の方への導入にオススメです♪

サイクルトレーニングのデメリットについて
そんなサイクルトレーニングでやはりデメリットもあります。
・サイクル終盤でピークを合わせられない
4週目に必ずしもピークが来る、良いコンディションとは限りません。
目標値を高望みし過ぎる、風邪ぽい、仕事やプライベートで忙しくて休養不足など・・・だって人間だもの笑
・サイクル終盤でフォームが荒くなる
終盤で良いコンディションであれば良いのですが、そこまでコンディションが優れていない場合は・・・。
定数の目標数値に囚われてしまい無理やり決行してしまいます(だって前の3週間が無駄になるんだものw)。
結果的に成長に繋がらなかったり、怪我のリスクを増やしてしまいます。
・一定期間レップ数が固定される
8レップなら8レップを数ヶ月間実施することになるので、レップ数を変位させる対応力は低下します。
レップ数が固定されると刺激のマンネリ化の原因となりえるかもしれません。
などになります。
そこでRPE(主観的運動強度)もしくはRIRを用いたサイクルトレーニングが良いのかなと思います。
主観的運動強度:RPEについて
筋力向上では1RM80%~90%ぐらいで挙上スピードを意識した方が伸びるとされています。
そこで、全力ではなくある程度力加減をしてトレーニングをする際にRPEやRIRといった表現をします。
RPEとはRating of Perceived Exertionの略になり、自覚的運動強度もしくは主観的運動強度のことです。
簡潔に言うと「その運動がどれくらいしんどかったか」を数字で表したものになります。
| RPEの例 | 説明(パワーリフティングでよく用いられる表現) |
| 10 | ギリギリ挙げた、文字通り限界 |
| 9 | 粘って挙げた、頑張って挙げた |
| 8 | 少し粘る、少し頑張った |
| 7 | ほぼ※粘らずに終えられた |
| 6 | ウォームアップのように行える |
これはRPE6くらい
— ふんどしのための肉体改造|義田 YouTuber & 浜田山/西永福のジムオーナー (@theapokici) October 13, 2025
実際、最終アップはこれでいきます👍 pic.twitter.com/E7TosX8wej
筆者のデットリフトでRPE6のイメージです。
これはRPE8.5くらいかな
— ふんどしのための肉体改造|義田 YouTuber & 浜田山/西永福のジムオーナー (@theapokici) October 13, 2025
主観的運動強度なので自分(動画なら永井さん)基準ですが pic.twitter.com/6DFEt5XxhO
永井肇選手のデットリフトでRPE8~8.5のイメージです。
RIRとはReps In Reserveの略であり、あと何回できたか?を表したものになります。
RIR2とはあと2回出来たというイメージです。
| RIRの例 | 説明 |
| 0 | もう限界 |
| 1 | あと1回できる |
| 2 | あと2回できる |
| 3 | あと3回できる |
| 4 | あと4回できる |
このRPEやRIRを意識してトレーニングを実施します。
1レップだけでなく、5や8、10レップでも最終レップのときの感覚でRPEを決められます。
例えば、スクワット150㎏5回実施してみて5回目で少し粘った、頑張ったとしたらRPE8ということになります。
今回はRPEベースで新サイクルトレーニングのやり方を提案します。
新サイクルトレーニング!RPEベースでプログラムしよう♪
一般的にサイクルトレーニングは数値を決めて実施しますが、これをRPEベースで実施すると先ほどのデメリットを解消できるかもしれません。
その日のコンディションでの主観的運動強度で良いですので、数値に囚われて無理をする心配もありません!
RPE9を@9と表記することもあり、今回は@を用いて説明します。
例えば、5レップをベースで実施するなら
Week4:5レップ@9を2セット
Week3:5レップ@8を2セット、3レップ@8を2セット
Week2:5レップ@7を2セット、3レップ@7を2セット
Week1:5レップ@6を2セット、3レップ@6を2セット
みたいになり、これはシンプルにまとまって分かりやすいですね。
ちなみにRPEベースですのでセット毎に重量が変わる可能性もあります。
Week3で150㎏5レップ実施して1セット目で@8、次実施したら@8越えそうなら145㎏5レップなど重量をいじることもあります。
もしくは、2セット目150㎏で実施して4回の時点で@8だったら4回で終わりにする方法もあります。
1サイクル目
Week4:8レップ@9を2セット
Week3:8レップ@8を2セット、5レップ@8を2セット
Week2:8レップ@7を2セット、5レップ@7を2セット
Week1:8レップ@6を2セット、5レップ@6を2セット
2サイクル目
Week4:5レップ@9を2セット
Week3:5レップ@8を2セット、3レップ@8を2セット
Week2:5レップ@7を2セット、3レップ@7を2セット
Week1:5レップ@6を2セット、3レップ@6を2セット
3サイクル目
Week4:1レップ@9を2セット
Week3:1レップ@8を2セット、3レップ@8を2セット
Week2:1レップ@7を2セット、3レップ@7を2セット
Week1:1レップ@6を2セット、3レップ@6を2セット
みたいにサイクル周回毎に狙いのレップ数を動かすのもアリかなと思います。
こうすることで刺激のマンネリ化を抑制し、対応力を付けることが出来ます。
主観的運動強度RPEのデメリットについて
デメリットとしては慣れるまで数値の感覚を掴むのが難しいかもしれません。
性格によって強がりな人は、結構粘っている(頑張っている)のに今のは@6!とかあります笑
これをオーバーシュートといい筋力向上において避けたい状態です。
逆に謙虚な人は、かなり余裕あるのに今のは@9・・・となり、これをアンダーシュートといいオーバーシュートよりは良いですが、やはり目標達成しにくいです。
主観的運動強度ですので自分で決めることですが、最初のうちはトレーニング時の動画を撮影してよく見返したり、周りのトレーニーにどうだったかを確認するのもアリですね。
また、実際にメインセット実施してみて例えば@7狙いだったのが@6だったら、そのセットはノーカウントにして少し重量を増やして1セット目を実施することもあり得ます。
もしくはセット数が3とかでしたら、1セット目を実施したとして2セット目は少し重くするなど調整するのも良いです。
慣れてきたらウォームアップの段階で何となくRPEと重量の目星を付けることが出来ますので、とにかくRPEの概念に慣れていきましょう!
VBTのような速度管理ツールを用いてRPEを求めるのもおススメです。
・トレーニングの新常識”VBT”について
https://zero-fitness.com/about-the-new-vbt-in-training/
まとめ
サイクルトレーニングは管理しやすく目標を立てやすい素晴らしいトレーニングプログラムです。
しかし、サイクル終盤に必ずしもピークを作れない、コンディションが優れないこともあります。
ここで無理をするとフォームが雑になり、結果的に怪我のリスクを増やしてしまうかもしれません。
そこで、主観的運動強度RPEを取り入れてその日のコンディションに素直になってトレーニングを実施します。
サイクルトレーニングで停滞したら、まずRPEの概念に慣れてRPEベースのサイクルトレーニングを実施していきましょう!
サイクルトレーニングは数値目標を立てやすく(モチベーションになりやすく)、初心者~中級者くらいでしたら成長期ですので数値目標を達成しやすいです。
中級者以上になったら成長も緩やかになると思いますので、RPEベースのサイクルトレーニングを導入してみると良いでしょう。
以上になります!
当パワーフィットスタジオZEROでは、他のフィットネスジムよりもフリーウェイトに特化したフィットネスジムであり、トレーニング中級者以上の満足度の高い良いトレーニング環境となるでしょう!
あと、パーソナルトレーニング指導もしておりますので、スクワット、ベンチプレス、デットリフトをしっかりと学びつつ、他のダンベルやマシン種目なども学んでボディメイクもしたい方にもおススメです。



初回ビジター利用無料やパーソナル初回無料になりますので、興味のある方は下記のお問い合わせフォームにてご連絡お待ちしております!
↓
初回無料体験や見学、初回無料パーソナルトレーニングにつきましては事前に以下の方法でご連絡をお願い致します
電話番号:080-5140-0679
メールアドレス: postmaster@power-fit-studio-zero.com
お問い合わせフォーム
公式LINEはこちら↓
あなたへのおすすめ記事↓
ベンチプレスを強くするための補助種目とその理由
高糖質食こそが強くなる秘訣!筋力向上に向いた食事方法について